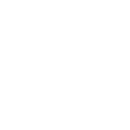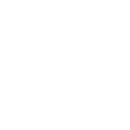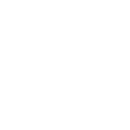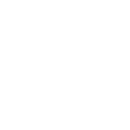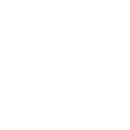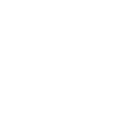トピックス
具体的な付加金の対策方法(弁済供託等)について
2024/04/02
はじめに
労働基準法114条において、未払い残業代等について、労働者が請求した場合には、裁判所は、未払い残業代等の他に、これと同額の付加金の支払を命ずることができるとされています。つまり、訴訟において、会社が残業代未払いで敗訴する場合、判決では、会社側は未払い残業代額の倍の金額の支払を命じられる可能性があるということになります。
(例えば、訴訟において、未払い残業代額が200万円と認定された場合に、この残業代200万円とは別に付加金200万円の支払が命じられることがあります。)
小コラム:付加金が命じられるかの判断要素
判決において、付加金は必ず命じられるものではありません。この点、大阪地裁平成13年10月19日判決では、付加金を命じるか否かの判断要素として、次のように判示しています。
「付加金の支払請求については,使用者による同法違反の程度や態様,労働者が受けた不利益の性質や内容,前記違反に至る経緯やその後の使用者の対応などの諸事情を考慮してその支払の可否及び金額を検討するのが妥当である。」
付加金への対策
付加金の問題は会社側(雇用主側)にとっては重大な事柄なのですが、付加金で調べていただくと、「付加金は、控訴して、残業代を支払ってしまえばよいので、そこまで気にしなくてよい」というようなインターネット情報が散見されます。この点、確かに、私(本コラム筆記者:弁護士高橋)も、以前は、上記のように考えていましたが、実際の手続等をより深く考えると、この付加金への対応は奥が深く、難しいものであると感じています。
付加金を命じられた後の対処方法(弁済供託等)について、現時点で私が考えていることを解説いたします。
付加金対策の基本的な理解
前述のとおり、付加金は、訴訟において裁判所に命じられるものですが、その支払請求権は、付加金を命じた判決が確定して初めて具体化します。この点を捉えて、弁護士業界での付加金対策の手法としては、控訴をして第一審の判決の確定を遮断し、控訴審係属中に、未払い残業代の元本につき、弁済又は弁済供託をして、控訴審において弁済の抗弁を主張すれば、残業代元本が消滅しているため、同元本の存在を前提とする付加金は、控訴審判決では命じられない(付加金の支払を免れることができる)、と考えられています(最高裁平成26年3月6日判決参照)。
付加金への対策で注意すべき点
上記は、一般的な理解としては間違っていないのですが、ここで気になる裁判例として、東京高裁令和4年3月2日判決(三井住友トラスト・アセットマネジメント事件)(以下「東京高裁令和4年判決」と言います)があります。この東京高裁令和4年判決では、控訴中に会社側がした残業代元本の弁済供託は、解除条件付の弁済供託に過ぎず、任意の弁済とは認められないから、残業代元本の消滅原因(弁済の抗弁)と認められない、と判示されています(結論として、弁済供託したにもかかわらず、残業代の支払いが命じられています。)。
この件については、最終的な付加金の判断として、悪質性がないから付加金を命じないとされており、結論においては、付加金が命じられていないのですが、上記の弁済供託の部分の判示を見ると、弁済供託しても、任意の弁済と認められない限りは、弁済の抗弁として認められない(付加金に対する対策にはならない)ように読めます。
また、別の裁判例として、東京高裁令和元年12月24日判決(社会福祉法人恩賜財団母子愛育会事件)(以下「東京高裁令和元年判決」と言います)では、法人側(雇い主側)は、残業代支払いを命じた第一審判決の部分には控訴せず、付加金部分のみを控訴して、控訴審中に、残業代額を弁済供託しています。
この事案については、事実審である控訴審の口頭弁論終結までに、残業代元本が消滅したため、付加金は発生しないと判示されています。
おそらく、上記東京高裁令和元年判決の事件の法人側の代理人弁護士は、前記の東京高裁令和4年判決のような理論があり得ることを前提に、残業代部分については控訴をせず、残業代については争いのない確定債権にして、これに対して弁済供託をしているものと考えられます。
残業代請求部分についても控訴し、弁済供託をした場合に、必ず、東京高裁令和4年判決のような判断(弁済の抗弁として認められない)がなされるのかは定かではありませんが、付加金命令の防止を考えるうえでは、十分に注意が必要です。
考え得る付加金への具体的な対策(方法)
現時点では、私が会社側代理人として、第一審において付加金支払命令が出た場合には、次の方法を取ることを考えています。【方法①】(基本的に、前記東京高裁令和元年判決の法人側の手法と同様)
・残業代部分については、控訴せず(残業代請求権は確定)、付加金部分のみ控訴する。・第一審で命じられた残業代+遅延損害金を、その労働者の給与振込み口座へ支払う(※明示的に、労働者側代理人から「振込むな」等のアクションがない場合)。
・明確に受領拒絶がある場合には、受領拒絶を供託原因として弁済供託をする。
・その後、控訴審において、残業代は支払った旨の弁済の抗弁を出す。
【方法②】
・残業代部分及び付加金部分を、ひとまず全部控訴する。・控訴審では、和解協議となることが多いので、付加金無しの内容で和解を目指す。
・和解協議が決裂して結審(事実審の口頭弁論終結)してしまったら、残業代請求部分のみ控訴を取下げて確定させ、すぐに弁済又は弁済供託をし、弁論再開の上申を行う(弁済事実は重要な事実であるので、口頭弁論を再開してくれると考えていますが、再開してくれないリスクもあります)。
弁済供託について
なお、ここで弁済供託の方法についても述べておきたいと思います。ケースバイケースだとは思いますが、せっかく弁済供託をしても、受領拒絶等の供託の要件を満たさない無効な供託と争われるのは不本意です。
したがって、私であれば、次のような手順を踏んで弁済供託を行います。
本来的には、残業代は、労働者の給与支払い口座へ振り込んでよいはずです(本旨弁済になるはずです)ので、未払い残業代は、給与振込み口座へ振り込みます。
明示的に、労働者側代理人から、「振込むな」等のアクションがあった場合には、再度、受領を催告(給与支払い口座へ支払う準備ができている旨を再度通知する)し、それでも振込を拒絶するようであれば、弁済供託をします。
付加金について、より複雑な考察
なお、さらに難しいのが、第一審判決の残業代の認定において、一部、会社側に有利な判決内容となっている場合です。例えば、第一審判決で、固定(みなし)残業代制度の主張が会社有利に判断され、未払い残業代の支払があまり命じられなかったが、控訴審では固定残業代制度の部分で異なった判決(会社側に不利な判決)がされそうというような事案です。
この場合には、万が一、第一審と異なり、控訴審で残業代部分の請求が労働者側の請求のとおりに認められてしまうと、そもそも、控訴審で弁済又は弁済供託をするという時間を与えられずに、控訴審判決でいきなり残業代+付加金命令という判決がなされることになります。
このようなケースの対策方法は、私の中でも確立していませんが、現時点での考えでは、もし控訴審で第一審の残業代の認定が覆りそうだと強く考える場合には、労働者が請求している残業代額全額を弁済又は弁済供託してしまうのも一つの手(それを控訴審で抗弁とする)と考えています。
つまり、控訴審で、残業代+付加金の支払を命じられるリスクと、労働者が請求している残業代全額を弁済(弁済供託)することの不利益を天秤にかけて考えるということになります(第一審において、残業代部分で勝訴しているのに、請求されている残業代額を全額支払うということに、依頼者(会社側)が同意してくれるかはとても難しい問題ですが、控訴審での裁判官の顔色(審理内容など)を見つつ考えることになると思われます。)。
最後に
残業代請求訴訟に伴う付加金の問題は、上記のとおり難しい問題を含んでいます。当事務所では、会社側・経営者側の労働問題を専門的に取り扱っていますので、お困りの場合には是非ご相談ください。
◇ 横浜で会社・企業側の労働問題に強い弁護士をお探しなら、当事務所へご相談ください!
ご予約はTEL(045-594-8807)又はメール予約をご利用ください。
労働基準法
(付加金の支払)
第百十四条 裁判所は、第二十条、第二十六条若しくは第三十七条の規定に違反した使用者又は第三十九条第九項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から五年以内にしなければならない。